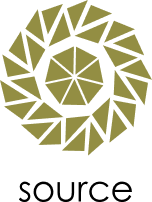- ブログ
『はじめての金継ぎ』ワークショップ開催しました!

こんにちは、source storeのMです。3月7日と8日の2日間、source store本店にて現代金継ぎを体験していただくワークショップ『はじめての金継ぎ』を開催いたしました。昨今話題の金継ぎではありますが、想像以上にお申し込みをいただき、おかげさまで募集開始からあっという間に満席、キャンセル待ちとなりました。私たちsource storeでは、家具を通じて「物を大切にする心」をとても大切にしています。ひとつひとつの物が持つ背景や記憶、暮らしの中で感じる日々の愛着など、今回のワークショップをとおして、ご自分が大切にしているものへの想いが、より豊かで深いものになればと考え企画しました。
お持ちいただいたお気に入りの器のストーリーは皆さんそれぞれ違いますが、欠けてしまった大切な器に自分の手で新たな魅力を加える喜びには、一様にご満足いただけたのではないでしょうか!
■金継ぎとは
金継ぎとは、日本に古くから伝わる器の修復技法のひとつです。漆で接着した器の割れ目や欠けを、金粉や銀粉で美しく装飾し、新たな魅力を与えます。
「壊れたからこそ生まれる美しさ」を楽しむこの技法は、日々の生活の中での物との向き合い方を教えてくれます。
今回のワークショップでレクチャーいただいたのは、伝統的な材料(本漆)を使わず、手軽に短時間で完成する簡易的な金継ぎです。メリットは、かぶれない、工程が少ない、時間がかからない、すぐ使用できるなど、現代の利便性やスピードに合わせた新しい金継ぎのスタイルです。当日は、本漆を使用した様々な金継ぎが施された器もご展示いただきました。中には朱色のものや螺鈿が施されたものもあり、私たちスタッフもはじめてまじかに見ることができ興味津々。
 |
 |
講師にはフードコーディネーターでもあり、名古屋で陶磁器修理の金継ぎワークショップを主宰されているオフィストランセット 上村 尚美様をお招きし、はじめての方にもわかりやすい軽妙なトークで盛り上げていただきました。
※オフィストランセット 上村 尚美様のインスタグラムはこちらから
■ワークショップスタートです!
まずは皆様にお持ちいただいた器が、今回のワークショップで修復可能かどうかを先生に見ていただき、ご自身でも欠けの具合を丁寧に確認していきます。
そのあとお手本に直に触れていただきながら、完成品の感覚を指でなぞって仕上がりをイメージ。先生からの『今日一日、指3本の腹の感覚を研ぎ澄ませて』の声に、皆さんの集中力も上がります。

 |
 |
修復箇所を覚え込んだら、スピード勝負で欠けた部分をパテで埋め込みます。確かに対象箇所を覚えていないと器によってはどんな”欠け”だったか、とてもわかりづらくなっていました!
乾いたら次は余分な部分を研ぎ、なめらかで違和感のない仕上がりにしていきます。小さな修復箇所ですが、思いのほか時間がかかります。先生の励ましの声を受けながら!?(笑)、細かな作業が続きます。簡単には先生のOKがもらえず、より一層集中力が増した皆さんのサンドペーパーをかける音だけが際立ってきました。

 |
 |
次の工程は塗りの作業です。道具を小さい筆に持ち替えて溶液を塗っていきます。だいぶ金継ぎらしくなってきました!修復した箇所がアクセントにもなって、器がよみがえっていきます。

最後の仕上げは先生によって施される『蒔き』と呼ばれる作業でした。まんべんなく蒔かれた金粉によってさらに素敵な仕上がりに!
作業時間はおよそ1時間半、長時間の集中お疲れ様でした!!!
■先生を囲んでのティータイム

作品を乾燥させている間は、先生を囲んでのティータイム。季節のお菓子と薫り高いお茶を召し上がっていただきながら、金継ぎについての質問など、おしゃべりも弾みます。
■店内で出来上がりを確認しながら記念撮影!


完成後はお互いの作品を撮影しあったりと、思い思いに店内で記念撮影!自分たちの手であらたに生まれ変わった器に、先生も参加者の皆様も大満足のご様子!上記のお写真は、今回ご参加いただいた皆さまの作品です。それぞれの想いが詰まった器たち、小さく丁寧に仕上げられた修復箇所、写真ではなかなかお伝えしにくいのが残念ですが、ぜひご覧ください!

ご参加いただきました皆様、講師の上村様、2日間にわたり有意義なお時間を頂戴いたしましたことに、スタッフ一同感謝申し上げます。
ご好評いただきました現代金継ぎのワークショップは、次回はsource store青山店にて今秋開催予定です。
詳細決まり次第、当サイトをはじめ、メルマガやインスタグラムでもご案内いたします。ぜひチェックしてみてくださいね!